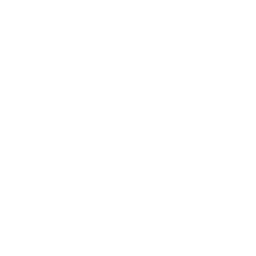作成日:2023年05月31日 更新日:2025年01月30日
女性にスクワットをおすすめしたい本当の理由

「YouTubeで見よう見マネでやってみたけど、スクワットの正しくやり方がかわからない、、、」
「スクワットをして脚が太くなったような気がする、、、」
あなたもスクワットをして、こんな風に感じていませんか?
自分自身の筋トレを行なっている際に、いろんな人のスクワットを見ていると、横からアドバイスをしたくなるぐらい、危険なフォームでスクワットを行なっている人も多くいます。
スクワットの形をマネするだけなら、トレーニングの知識などは必要ありません。
今回の記事では、これまで多くの方のトレーニングをアドバイスしてきた経験と、解剖学の知識を織り交ぜ、運動が苦手な女性でもわかりやすいように、正しいスクワットのやり方、効果について解説していきます。
目次
スクワットの効果
スクワットを行うことで、女性には嬉しい様々な効果があるのですが、今回は5つご紹介します。
スクワットの効果
- メリハリのあるボディになる
- 若返り効果
- 美肌効果
- 痩せやすい身体になる
- むくみ・冷え性の改善
この5つの効果について詳しく解説します。
メリハリのあるボディになる

スクワットを行うことによって、メリハリのある身体を作ることができます。
スクワットではふくらはぎ〜お尻周りの筋肉を鍛えることができ、脚は引き締まり、ヒップアップ効果もあり、メリハリのある身体を作ることが可能です。
年齢を重ねると、筋肉は衰え、弛んでしまい、締りのない身体になり、太りやすくもなってしまいますが、スクワットを行うことで、それを改善することができます。
メリハリのある身体になることで、着たい服が着れるようなり、自分に自信が持てるようになるのです。
また下半身に、身体の60%〜70%の筋肉が集中しているので※1、スクワットで身体の半分以上の筋肉を鍛えることができるので、非常に効率的です。
女性が望むメリハリのあるボディラインを作るには、スクワットは重要な種目になります。
若返り効果

スクワットなどの筋トレをすることで、若返り効果があることがわかっています。
筋トレをすることによって、若返り効果がある成長ホルモンが多く分泌されるのです。※2
成長ホルモンは、若返りという点において非常に重要な役割を果たすホルモンと認識されていますが、年齢を重ねると分泌量は減少してしまいます。
しかし、トレーニング直後は年齢に関わらず、トレーニングをすることで分泌量が多くなるので、若返り効果があると言えるのです。
美肌効果

スクワットをすることで、美肌効果にもつながります。
あまり接点がないように思われるかもしれませんが、研究で証明されているのです。
筋肉で作られる「マイオネクチン」という成分が、シミの原因となる「メラニン」を抑えるので美肌効果があるのです。※3
また、下半身の筋肉量が多いほどシミが少ない※4 真皮という肌の弾力性に関係する組織が厚くなることがわかっています。※3
真皮が厚い方が、シミ・シワ・顔のたるみが少なく年齢よりも若く見られやすいのです。※3
スクワットをすることによって、身体の半分以上の筋肉を鍛えることができ、結果的に美肌効果につながるのです。
筋トレの美容効果に関するブログをまとめているので、是非参考にして下さい。
痩せやすい身体になる

スクワットを行うことによって、痩せやすい身体になります。
スクワットで、身体の半分以上の筋肉を鍛えることができると、ご紹介しました。
筋肉がつくことで、基礎代謝が高くなり、1日の消費カロリーも多くなるので、痩せやすい身体になるのです。
むくみ・冷え性の改善

スクワットを行うことによって、女性が悩まれているむくみ・冷え性の改善につながります。
むくみは血液循環が悪いことでおり、冷え性は基礎代謝が低いことが原因で起こります。
スクワットを行うと、血液循環は良くなり、基礎代謝も高くなるので、むくみも冷え性も改善されるのです。
女性が筋トレをするメリットについては、別のブログでもまとめているので、ぜひ参考にして下さい。
スクワットはトレーニングのキング!

トレーニング業界でスクワットは「キング・オブ・トレーニング」と言われています。
スクワットを行うと、足首・膝・股関節の3つの関節が動くので、関与する下半身のほとんどの筋肉を鍛えることが可能なので、トレーニングの王様と表現されるのです。
身体全体の6割〜7割の筋肉が下半身に集中しているため※1 スクワットによって、身体の半分以上の筋肉を、鍛えることが出来るということになります。
このことから筋トレをするうえで、スクワットを避けることはできないのです。
正しいスクワットのやり方
スクワットの正しいやり方について説明します。
誤ったフォームでトレーニングをしてしまうと、正しい効果が得られないだけでなく、ケガの原因となってしまうので、安全で効果的な正しいフォームを身に付けてトレーニングを実践しましょう。
正しいスクワットのポイント
- 脚の幅は肩幅
- つま先は約30度ほど外向き
- 太ももが床と平行になるところまで、お尻を突き出すようにしゃがむ
- しゃがむ時の動作はゆっくり3秒かけてしゃがむ
- 立ち上がる時は、踵で踏ん張る意識でテンポ良く立ち上がる
スクワットの注意点

スクワットの注意点について4つご紹介します。
背中が丸まってしまう
動画のように背中が丸まってしまうと、腰に痛めることになってしまいます。
腰が丸まらないように、背中は真っ直ぐの姿勢になりように心がけましょう。
膝とつま先の向き
スクワットでは、膝とつま先の向きが同じになるようにしましょう。
よくある例としては、膝がつま先の位置よりも内側になってしまう例です。
これは女性によく見られる現象で、お尻の筋肉が弱いなどの理由が考えられます。
膝が中心にならない
スクワットの動作が膝中心になってしまうと、お尻や太もも裏の筋肉が鍛えられにくく、太ももの前の大腿四頭筋が鍛えられてしまい、脚が太くなってしまいます。
また、膝を傷めてやすくなるので、注意が必要です。
スクワットの応用
基本のスクワットが正しくできるようになったら、変則的なスクワットにも挑戦してみましょう!
刺激される筋肉も、変化するので、総合的にみるとトレーニングの効果が向上します。
今回は3つご紹介しますので、トライしてみて下さい。
ツイストスクワット
ツイストスクワットは、よりお尻を鍛えることができる種目です。
ツイストスクワットのやり方
- 両足を合わせた状態で立ちます
- 片方の脚を45度後方に大きくクロスします
- クロスした側の膝を真下に降ろします
- 踵を意識して立ち上がります
- 重心は常に前側の脚にあるようにします
※常に重心が前になるように意識しましょう。
スタガードスクワット
スタガードスクワットは、スタンダードなスクワットよりも強度が高いスクワットです。
片足を半歩前に出して行うので、前に出している脚に、より負荷がかかりお尻などが鍛えられるスクワットになります。
通常のスクワットより、強度を高めたい時にオススメのスクワットです。
スタガードスクワットのやり方
- 片足を半歩、前方に出し重心をかけます
- 後の脚は、踵を上げつま先立ちの状態にします
- 若干お尻を引き上体を倒しながら、しゃがみます
- 踵を意識して素早く立ち上がります
※トレーニング中は、常に重心が前の脚にかかっていることがポイントです。
ブルガリアンスクワット
ブリガリアンスクワットは、片方の脚をベンチなどに上げ行うスクワットです。
より強度高いスクワットで、お尻、太ももの裏の筋肉が鍛えることができます。
特に、よりお尻を鍛えたい女性におすすの種目です。
ブルガリアンスクワット
- 片足をベンチやソファーなど台の上にのせます
- お尻を引き、上体を倒し、軽く膝を曲げます
- 上げている側の膝を真下におろし、太ももが床と平行になるところまでスクワットします
- 斜め上(上体の角度)と踵を意識して立ち上がります
※上半身が垂直になり過ぎない(太ももの前が鍛えられやすくなる)
※前の脚の踵が浮かない
まとめ
今回のブログでは、スクワットについてまとめました。
効果的なトレーニングではあるものの、正しいスクワットを習得するのは難しい側面もあります。
安全で効果的な正しいスクワットを理解し、あなたのダイエットやボディメイクに是非役立て下さい。
参考文献
※1 荒川裕志.プロが教える筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト辞典.ナツメ社,2012,271p.4816353267,9784816353260.(参照2023年6月2日)
※2 Kraemer WJ, Gordon SE, Fleck SJ, Marchitelli LJ, Mello R, Dziados JE, Friedl K, Harman E, Maresh C, Fry AC. Endogenous anabolic hormonal and growth factor responses to heavy resistance exercise in males and females. Int J Sports Med. 1991 Apr;12(2):228-35. doi: 10.1055/s-2007-1024673. PMID: 1860749.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1860749/,(参照2023年6月2日)
※3 株式会社ポーラ化成工業(株)フロンティアリサーチセンター.“筋トレ(レジスタンス運動)が美肌を作る”.ポーラ化成工業株式会社.2020-10-16. http://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20201016_05.pdf,(参照 2023年6月2日)
※4 株式会社ポーラ化成工業(株)フロンティアリサーチセンター.“美肌体質の秘密ー筋肉が“鍵”を握ることを発見”.ポーラ化成工業株式会社.2018-09−25.http://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20180925_3.pdf,(参照2023年6月2日)
著者プロフィール

佐藤 喜一
鍼灸師としての医学的観点とトレーナーとしての科学的視点をかけ合わせ「あなた本来の身体」へ導くパーソナルトレーナー
指導実績
トップアスリート、アーティスト、モデル、俳優などのトレーニング&コンディショニングを担当 これまでの経験を基に、トレーニングと鍼灸で1,000名以上の身体の悩みを抱える方々のサポートを行う
保有資格
◆はり師・きゅう師 ◆NSCA-CPT(認定パーソナルトレーナー) ◆FMS Level1 ◆テクニカ・ガビラン認定者