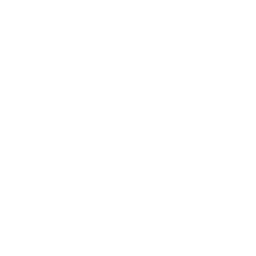作成日:2023年01月12日 更新日:2025年01月30日
筋トレの効果はストレッチ のタイミングで左右される?

「筋トレ前後ってどんなストレッチ をしたら良いの?」
「筋トレをする前はストレッチ しちゃダメって聞いたんだけど、本当はどうなの?」
あなたは、こんな疑問をもったことはありませんか?
結論、筋トレ前にストレッチ は行っても問題はありません。
しかし、筋トレ前後で行うべきストレッチ は異なり、筋トレ前に向いているストレッチ 、筋トレ後に向いているストレッチ があります。
一言で「ストレッチ 」と言っても数種類があるので、タイミングによって行うストレッチ が違います。
今回の記事では、筋トレ前に行うストレッチ ・筋トレ後に行うストレッチ を解説し、トップアスリートやアーティスト、モデルさんのトレーニング前後で指導していた、おすすめのストレッチ もご紹介します。
目次
筋トレの前と後で行うストレッチ は違う?
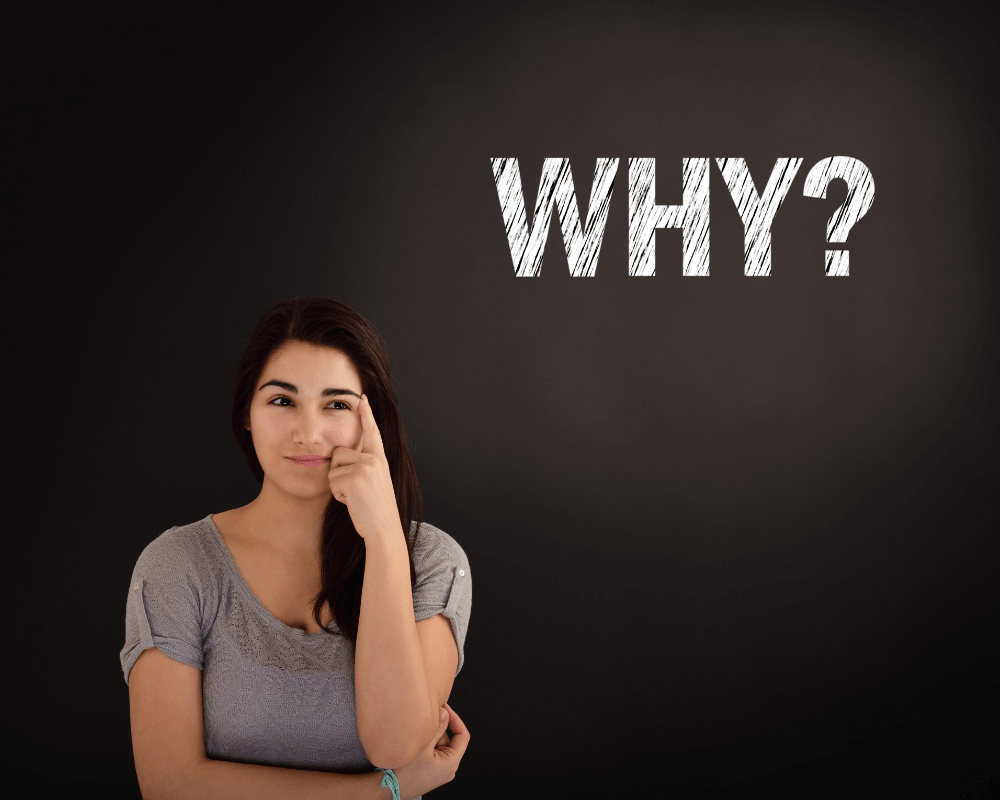
筋トレ前と後で行うべきストレッチ は違います。
筋トレ前は、動的ストレッチ
筋トレ後は、静的ストレッチ
を、行うのが一般的です。
同じストレッチ でも、タイミングと目的が若干異なるので使い分けが必要になってきます。
動的ストレッチ と静的ストレッチ が、どのような違うのか解説します。
動的ストレッチとは?

動的ストレッチ とは、動きの中で行うストレッチ のことをいいます。
動的ストレッチ は、主にトレーニングや様々なスポーツを行う前に、①動作の円滑化、②関節可動域を広げるために行われ、パフォーマンスの向上、怪我の可能性を軽減することを目的に、ウォーミングアップの初期のタイミングで取り入れられます。
また、クールダウンに取り入れることによって、身体の血液循環を良くし、疲労物質を除去されるメリットもあるのです。
動的ストレッチ は「バリスティックストレッチ 」と「ダイナミックストレッチ 」の2種類に分けられ、トレーニングのウォーミングアップに取り入れる際は、この2つをミックスして行うと、より効果が向上しおすすめです。
バリスティックストレッチ
勢いや反動をつけて筋肉を伸ばし、筋肉の弾性力を高めるメリットがあります。
セルフで行う場合と、パートナーに行ってもらうやり方があり、パートナーに伸ばしてもらう際は、伸ばし過ぎると「伸長反射」という防御反応が働いてしまい、身体が緊張してしまい、ストレッチ 効果が薄れてしまうので、注意が必要です。
ダイナミックストレッチ
ダイナミックストレッチ とは、伸ばしたい筋肉(主動筋)と反対方向に動く筋肉(拮抗筋)を意図的に動かし、この動作を繰り返し行うことで、伸ばしたい筋肉(主動筋)を弛緩させるストレッチ のことをいいます。
動画のように、膝を意図的に曲げて、太ももの裏の筋肉(反対方向に動く筋肉)を動かすことによって、太ももの前(伸ばしたい筋肉)をストレッチ することが可能です。
静的ストレッチ

「ストレッチ 」といわれれば、この静的ストレッチ が指されるのが一般的です。
静的ストレッチ は、スタティックストレッチ とも表現され、反動はつけずにゆっくり呼吸をしながら筋肉を伸ばします。
静的ストレッチ を取り入れることで、①柔軟性の改善、②筋肉の緊張の緩和、③疲労物質の除去されるので、トレーニング後のクールダウンに取り入れるとメリットがあります。
筋トレを行うと筋肉は、短縮してしまい、元の状態に戻すには、この静的ストレッチ が有効になります。
スポーツ選手では、身体の疲労度を確認するために、ウォーミングアップ前のタイミングで、この静的ストレッチ を行われる多いのです。
筋トレ前の静的ストレッチはNG?
筋トレ前に静的ストレッチを取り入れている人がいますが、筋トレのパフォーマンスを低下させてしまうので、避けた方が良いでしょう。
これは静的ストレッチを行うと、リラックスしている時に活発になる副交感神経の働きが優位になるからです。
人は環境の変化が起こっても、身体の状態を一定に保とうとする働きがあり、これは自律神経が司っています。
自律神経には、活動が活発になるときに優位になる交感神経と、リラックスしている時に優位になる副交感神経があります。
筋トレを行うときは、交感神経が優位になりますが、筋トレ前にストレッチを行なってしまうと、副交感神経が働き力が入りにくくなってしまい、筋トレのパフォーマンスが低下しやすくなるのです。
このことからも、筋トレ前は、静的ストレッチではなく、筋トレに向けて交感神経を働くためにも動的なストレッチを行う方が効果的になります。
筋トレ前のストレッチ の効果

筋トレをする前は動的ストレッチ を行うことで
- 筋温が上昇することで筋出力の向上
- 可動域が広くなる
- ケガの可能性の減少
に、つながります。
ウォーミングアップが不十分だと、いつも挙げている重りが挙がらなくなったりしてしまいます。
また、筋トレは関節可動域が狭いより広い状態で行った方が効果的です。
そして、何よりケガに繋がってしまう可能性もあるので、トレーニング前は動的ストレッチ を行いましょう。
動的ストレッチ の前に以前ブログで紹介した、筋膜リリースを取り入れると、ストレッチ の効果も筋トレの効果をあがるメリットがあります。
筋トレ後のストレッチ の効果
筋トレ後にストレッチ を取り入れるなら、静的ストレッチ を行いましょう。
筋トレの後にストレッチ を行うことによって
- 筋トレによって緊張し短くなった筋肉を元に戻す
- 身体の疲労を取り除く
- 柔軟性の改善
などの効果があります。
ストレッチ の注意点
ストレッチ の注意点は、以下の3つです。
主に静的ストレッチ を行う際の注意点になります。
- ストレッチ は20秒〜40秒を目安にする
- 呼吸は止めない
- 筋肉を伸ばしている時は力加減を気を付ける
この3つがポイントになります。
筋肉が伸ばされると、センサーの役割をしている腱に伝わり、より筋肉を伸ばそうとするのです。
20秒以上、筋肉を伸ばしいるとこの現象が起こるので、ストレッチ は20秒〜40秒を目安にしましょう。
筋肉を伸ばしている時に、呼吸が止まってしまうと、身体が緊張してしまいます。
伸ばしたい筋肉もリラックスすることができず、ストレッチ の効果を発揮できなくなってしまうので、意識してゆっくりと深呼吸を行うようにしましょう。
ストレッチなしの筋トレは危険!

ストレッチを行わず、筋トレをすると怪我のリスクが高くなります。
平常時は、関節の可動域狭く、筋温も低く、心拍数も高くなっていない状態で、身体が適切な筋トレを行う状態ではないからです。
そんな状態で筋トレを行うと、筋トレの効果も薄くなり、腰なども痛めやすくなってしまいます。
これは、筋トレを始めたばかりの人もですが、筋トレに慣れている人こそ注意が必要です。
よくある例として、スクワットを行う時に、ストレッチを行わず、最初にバーベルだけの軽い負荷でスクワットを行い、ストレッチ替りにする人が多いくいます。
これは筋トレの準備としては、不十分です。
SNSなどの影響で、インフルエンサーのマネをして、同じようにしている人は、改めることをおすすめします。
ましてや、トレーナーがそれを推奨しているのは論外です。
スケジュールの都合で、十分にストレッチの時間を確保することができなければ、ジムに行くまでに自転車や歩いて行き、筋温を上げて状態で行くとよいでしょう。
ストレッチは不十分でも、ウォーミングアップ替りのバーベルだけのスクワットで身体をある程度ほぐすことができ、最低限のケガを防ぐことができます。
しかし、筋トレの効果を最大限にするためにも、ケガを予防するためにも、筋トレ前後のストレッチ込みで、筋トレの時間を確保するようにしましょう。
筋トレ前のストレッチ
筋トレ前におすすめのストレッチ を、3つ紹介します。
今日のトレーニングからでも取り入れることができるストレッチ など、是非やってみてください。
各種目ともに回数は10回〜12回、セット数は2〜3セットを目安に行いましょう。
ストレッチ 1
1.横向きになって、下側の足は真っすぐ伸ばし、上側の足の股関節・膝を曲げストレッチ ポール等にのせます。
2.下側の手で上側の膝を押さえ、上側の腕を開きます。
※この時、背中(肩甲骨周り)の筋肉を寄せる感覚で行うと効果が高まります。
3.最大限ひらいたら、息を吐きながら3秒キープします。
4.元のポジションに戻ります。
ストレッチ 2
1.両方の足を膝を伸ばして挙げます。
2.息を吐きながら、片方の足を降ろして3秒キープします。
※この時、降ろしている足を床に押し付ける、挙げてる足は太ももの前に力を入れるようにします。
3.元のポジションに戻ります。
ストレッチ 3
1.骨盤幅で立ち3〜4センチ程の段差に爪先を挙げます。
2.息を吐きながら、しゃがんだタイミングで3秒キープします。
この時に、身体が前屈みになりすぎない、爪先が外を向かない範囲で最大限しゃがみます。
3.元の姿勢に戻ります。
まとめ
筋トレ前後で行うべきストレッチ についてまとめました。
筋トレ前後にストレッチ を行うと、筋トレの効果が高くなるメリットがあり、質の高い筋トレができるので非常に重要です。
ストレッチは、軽視される傾向になり、簡易に済ませたり、取り入れていない人も少なくありません。
動的ストレッチ を行うか静的ストレッチ を行うかは、目的・タイミングで変わります。
「ストレッチ によって筋肉を損傷する」というデメリットがあるという記事を見かけたことがありますが、ストレッチ によって、筋肉を損傷する可能性は極めて低いです。
誤解を恐れず言うと、ストレッチ にメリットはあってもデメリットはないと言っても過言ではありません。
是非、このことは覚えておいてください。
著者プロフィール

佐藤 喜一
鍼灸師としての医学的観点とトレーナーとしての科学的視点をかけ合わせ「あなた本来の身体」へ導くパーソナルトレーナー
指導実績
トップアスリート、アーティスト、モデル、俳優などのトレーニング&コンディショニングを担当 これまでの経験を基に、トレーニングと鍼灸で1,000名以上の身体の悩みを抱える方々のサポートを行う
保有資格
◆はり師・きゅう師 ◆NSCA-CPT(認定パーソナルトレーナー) ◆FMS Level1 ◆テクニカ・ガビラン認定者