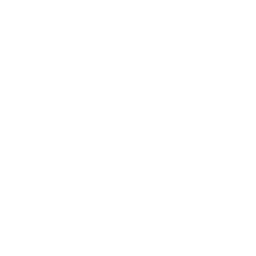作成日:2022年05月27日 更新日:2025年02月26日
必ず起こる?ダイエットの停滞期の原因と対処の仕方

「ダイエットを始めて、最初は順調に体重が落ちていたはずなのに、体重が落ちなくなった、、、」
「停滞期の時に、どんな対処をしたら良いのかわからない、、、」
ダイエットをしたことがある人であれば、停滞期で体重がまったく落ちない時期に遭遇したことはあるのではないでしょうか?
頑張って、普段の食べてる量を減らして気を付けているのに、体重が落ちない、、、
焦りの気持ちから、更に食べる量を減らしたり、よりハードな筋トレを取り入れたりした経験はありませんか?
結論からお伝えするとダイエットを行うと、身体にホメオスタシスという機能があり必ず体重は停滞してしまいます。
ダイエットを成功させ、目標を達成させるためには、この停滞期をどのように向き合うかがポイントです。
このブログでは、これまで1000名以上のダイエットをサポートしてきた経験と、鍼灸師として身に付けた体のメカニズム(生理学)の知識を組み合わせ、ダイエット中に起きる停滞期の原因をわかりやすく解説し、停滞期を抜け出す対策と行っていけないことをご紹介します。
停滞期で体重が落ちないと悩んでいる方は参考にして下さい。
目次
ダイエットにおける停滞期とは?
ダイエットの停滞期は、体重の減少が一時的に止まる時期をいいます。
体重が停滞するということは、ダイエットが順調に行われている証拠とも考えられることができ、ダイエットが失敗している、あなたの取り組みが間違っている、努力不足というわけではありません。
体重は減少と停滞を繰り返しながら減っていくのです。
停滞期は「ホメオスタシス※1」という身体の防御機能が正常に働いている結果であり、停滞期を乗り越えると、再び減少します。
したがって、停滞期で体重が減らなくても、焦ることもダイエットを諦める必要はなく、継続していくことが重要になるのです。
停滞期の原因
冒頭お伝えしたように、人はダイエットをすることによって、必ず体重が停滞してしまう生き物です。
なぜ人は停滞してしまうのか?その原因を解説していきます。
停滞期の原因
- ホメオスタシス
- ホルモンバランス
- 筋肉量の低下による基礎代謝の変化
この3つの原因について詳しく解説していきます。
ホメオスタシス
停滞期の1番の原因は先ほど、冒頭でもご紹介した「ホメオスタシス」という防御機能によって起こります。
人間の身体は、環境が変化しても一定の状態を保とうし、食事制限によって体重が減ると、身体は「飢餓状態になった!」認識し、エネルギーの消費を抑えようとするのです。
例えば、暑い時に汗をかいて体温を下げる、寒い時に震えて体温を上げて、身体の体温を一定にしようとするのものホメオスタシスの働きになります。
これと同様に、ダイエットによって摂取カロリーが減り体重が減ると、消費するカロリーを抑えようとし、停滞期が訪れるのです。
したがって、停滞期はホメオスタシスの機能によって起こる自然な現象であり、ダイエットが順調に進んでいる証拠でもあるので、ネガティブになる必要はありません。
ホルモンバランスの変化
女性場合はホルモンバランスの影響で生理1週間前ほどから、黄体期と呼ばれる期間で体重が+1kg前後増え、減りにくい状態になります。※2
これは女性ホルモンである、プロゲステロンというホルモンが機能し、排卵をきっかけに妊娠を維持しやすい状態を作るために栄養や水分を蓄えようとして、①食欲が増したり、②体重が減りにくかったり、③むくみやすい状態になるのです。※2
これが生理1週間前から停滞期にやりやすい原因となります。
筋肉量の低下による基礎代謝の変化

誤ったダイエットを行なってしまうと、筋肉量が低下してしまい、基礎代謝の低下につながる可能性があり、停滞の原因となってしまいます。※3
摂取カロリーを過度に減らしてしまうと、身体は筋肉を分解してエネルギーを作ろうとするのです。
筋肉が分解され、筋肉の量が減少してしまうと、基礎代謝の低下につながります。※3
基礎代謝とは身体が静止状態で消費するエネルギーで、人間のエネルギー消費の約60%を占めるのです。
モデルやインフルエンサーの食事やメディアなどによる誤ったダイエット法で、サラダだけの食事やバナナダイエットなどを行ってしまうと、タンパク質の摂取が極端に少なくなってしまい、筋肉量が減少する原因となってしまいます。
効果的なダイエットを行うには、食事の量だけでなく、食事の内容にも気を付けなければなりません。
停滞期が訪れるタイミング
停滞期が訪れるタイミングは個人差がありますが、ダイエットを始めて2〜3週間、1ヶ月の間に訪れます。※4
ダイエット開始から、体重が5%前後減った時に停滞しやすいと言われており、これには原因のところで解説したように、ホメオスタシスの機能が関係しているのです。
実際に、当施設に通われているお客様の体重の推移を見ていると、ダイエットを開始して2〜3週間、1ヶ月までの間に体重の5%前後減った人は体重が停滞しています。
これはあくまで目安であり、体重で左右されるので、身体の変化を注意深く観察することが大切です。
停滞期はどのぐらい続くのか?
どのぐらい停滞期が続くかは、個人差があります。
多くのお客様のダイエットをサポートしてきましたが、1、2週間で停滞期を抜ける人もいれば、1ヶ月停滞する人もいました。
もし3ヶ月以上停滞するようであれば、ダイエット方法を変えたり、食事や生活習慣を見直してみましょう。
停滞期からいち早く抜け出すために見直したいポイント
停滞期からいち早く抜け出すために、普段お客様にアドバイスしている5つのポイントをお伝えします。
なかな停滞期から抜け出せななくて困っている人は、参考にして下さい。
停滞期の5つの対策
- 効果的にチートデイを取り入れる
- 食事の見直し
- 睡眠
- 筋トレと有酸素運動
- ストレスの発散
効果的にチートデイを取り入れる
停滞期には、チートデイを取り入れるのが非常に有効的です。
チートデイとは、ダイエット中にドカ食いをしてあえて摂取カロリーを増やす日をいいます。
ダイエット中にそんなことして大丈夫?と思われるかもしれませんが、チートデイの1番の目的は、ホメオスタシス機能のリセットです。
身体に「十分にカロリーが入ってきている」と、認識させることが大切で、好きな物を食べることが出来るので、ダイエットのリフレッシュにもつながります。
チートデイは、一般的に1週間に1回、体重×40カロリーを目安にすると良いでしょう。(実際にカロリーは気にしなくてもOK)
ただし、チートデイは計画的に行うことが重要で、無計画で実践するとダイエットの効果がなくなってしまうので、注意が必要です。
以前の記事でチートデイの正しいやり方を解説しているので、是非参考にしてください。
食事を見直す

停滞期が1ヶ月以上続くようであれば、食事を見直してみましょう。
見直すポイントは
- 食事の量
- 食事の内容
この2つを見直してみてください。
食事の量
食事の量を見直してみましょう。
ダイエットに慣れてくると、知らず知らずに食べる量が増え、摂取カロリーと消費カロリーがイーブンになり、停滞の原因になっている可能性があるからです。
原則として、体重を落とすには摂取カロリーを抑え、消費カロリーをできるだけ増やしアンダーカロリーの状態が必須になります。
アンダーカロリーにするには、カロリー計算をするのが一般的ですが、体重の推移でもアンダーカロリーの状態にすることが可能です。
朝、起床後に体重を測定し、寝る前に測定します。
この時の差が、体重が身長−体重で100〜110に収まっている人は、400g以内。
収まっていない人は、600g以内になるように、食事の量をコントロールします。
例えば身長158cmで体重が55kgの人は400g以内
身長158cmで体重が62kgの人は600g以内にします。
朝と夜で、この規定内に収まっていなければ、食事の量は多い状態です。
主観的に腹八分目を意識して、体重がどのように推移しているか、まずは1週間注視しましょう。
食事の内容
食事の内容は、バランス良く食事ができているか確認しましょう。
栄養に偏りがあると、体重が停滞しやすくなります。
確認するポイントとして、糖質・脂質・タンパク質がバランス良く摂取できているか確認します。
- 糖質:50〜65%※5
- 脂質:20〜30%※5
- タンパク質:13〜20%※5
の、比率になるように心がけます。
糖質は、玄米や大麦などで摂取すると、血糖値の上昇を抑えることができるのでおすすめです。
ダイエットでタンパク質を摂取しようとすると、ささみやムネ肉を連想しがちですが、魚・豆腐・卵・赤身のお肉もバランス良く摂取しましょう。
また、脂質は様々な食べ物に含まれるので、意識しなくとも摂取することができので、意図的に取らなくても大丈夫です。
脂質をたくさん摂るケトジェニックなどもありますが、ダイエットは栄養をバランス良く摂取することを意識しましょう。
睡眠

睡眠も停滞的を乗り越えるうえで重要な要素です。
睡眠不足になると、「コルチゾール」の分泌が多くなり、食欲の増進につながってしまいます。※6
そうならないためにもまずは、6時間以上の睡眠を心がけましょう。
また、睡眠の質を高めるためにも、寝る1時間前からスマホなどでブルーライトを浴びない※7、食事は就寝3時間前には済ませるなど意識すると良いです。
そして、就寝の2時間前にはお風呂に入って深部温度を一時的に上げることもおすすめです。
深部温度が下がったきたタイミングで、睡眠を促し入眠をスムーズし、質の良い睡眠を得ることができます。※8
停滞期を打破すには、睡眠も関わるので、停滞期が抜け出せず悩んでいる人は、睡眠も見直してみましょう。
筋トレと有酸素運動
停滞期を乗り越えるために、筋トレや有酸素運動も一緒に取り入れてみましょう。
原因の項目で述べてたように食事制限だけでは、筋肉量を減少させ基礎代謝も低下させ停滞期を長引かせてしまう可能性もあります。
筋トレや有酸素運動など、適度な運動を取り入れて筋肉量を維持、増加させることで代謝を促すことができます。
大きいに筋肉を中心に筋トレを行い、その後に有酸素運動を行うと、脂肪燃焼も促され効果的です。
停滞期を乗り越えるためにも、食事と共に、筋トレと有酸素運動も取り組みましょう。
ストレスを発散させる

ストレスが蓄積されると、停滞期が長引いてしまうことがあるので、うまく発散できる方法をみつけておきましょう。
体重が落ちないことによってストレスも溜まりやすくなります。
それが原因となり、先ほど説明したコルチゾールが働きが強くなると、停滞期の時期が長引いてしまい、ダイエットに対するモチベーションも低くなり、ダイエットが失敗してしまうこともあるのです。
そうならないためにも、発散方法をみつけておくことが必要です。
チートデイも一つの方法ですし、筋トレや有酸素運動もストレスを軽減させる効果もあります。
友達と話をしてストレスを解消できるという人もいるでしょう。
停滞期を長引かせないためにも、自分自身にあった発散させる方法をみつけておきましょう。
停滞期の過ごし方
停滞期になったからといって、特別なことをする必要はありません。
これまで説明したように、停滞する原因はホメオスタシスという防御機能が関わっているので、ダイエットを行うほとんどの人が体重が減らないという状況に陥るからです。
実際に体重が停滞しているお客様にも、「特別なことをする必要はありません」と、お伝えしています。
体重が減らないからといって、ネガティブにならないようにというアドバイスもしています。
ネガティブになってしまうと、ストレスも大きくなり、前項で説明したコルチゾール の働きも活発になり、更に体重が減らないという悪循環になってしまうのです。
そうならないためにも、ネガティブにはならず、いつも通りに生活することが重要です。
停滞期にやってはいけない行動
停滞期にやってはいけない行動を3つご紹介します。
- 食事をさらに減らす
- 過度にトレーニングを行う
- ネガティブに考える
これらは飢餓状態を助長させてしまったり、ストレスを増加させてしまう要素になるので、注意が必要です。
食事をさらに減らす
停滞期を抜け出せず焦りから、食事を更に減らしてしまう人がいますが、これは絶対にやってはいけません。
食事の量を減らしてしまうと、体の飢餓状態をさらに助長させてしまい、停滞期を長引かせてしまう原因となります。
食事は「量」「質」「タイミング」をしっかり守りながら、停滞していても焦らず取り組みましょう。
過度にトレーニングを行う
筋トレや有酸素運運をハードに行っても停滞期を乗り越えるわけではありません。
食事の量を減らしていなくても、ハードに運動を行うと、消費カロリーが増えるので、身体は飢餓状態だと認識してしまいます。
これも停滞期が長くなってしまう原因となってしまうので、注意しましょう。
ネガティブに考える

体重が減らなくてもネガティブに考えるのは止めましょう。
ダイエットにおいて性格や思考は少なからず影響があると考えています。
これは、研究や論文で確認したわけではありませんが、これまで沢山の人のダイエットや筋トレをサポートしてきた経験での見解です。
ネガティブの人より、ポジティブな人の方が体重の落ちる幅も大きく、停滞期も早く抜けれる印象があります。※9
ダイエット中、特に体重が停滞している時は、チートデイなどでストレスを発散させつつ、ポジティブに考えることが必要です。
まとめ
今回の記事では、停滞期の原因や気を付けるポイントについてまとめました。
停滞期が訪れるということは、裏を返せばダイエット順調であるというサインでもあるので、焦らずチートデイ を取り入れ、生活習慣などを見直してみて下さい。
ダイエットを成功させるポイントは、息抜きしながら根気強く、そして長く継続するということです。
正しくダイエットを取り組み、あなたの理想とする身体を手に入れましょう。
参考文献
※1 東洋療法学校協会, 佐藤優子. 生理学. 東京: 医道の日本社; 2003. p. 2.(参照2025-02-15)
※2 Breckwoldt M, Keck Ch. Das Prämenstruelle Syndrom [Premenstrual syndrome]. Ther Umsch. 2002 Apr;59(4):183-7. German. doi: 10.1024/0040-5930.59.4.183. PMID: 12018036.(参照2025-02-15)
※3 Fagerberg P. Effects of severe energy restriction on body composition and skeletal muscle in physically active men and women. Nutr Metab (Lond). 2018;15:12. doi: 10.1186/s12986-018-0257-0. PMID: 29368656.(参照2025-02-15)
※4 Sarwan G, Daley SF, Rehman A. Management of Weight Loss Plateau. 2024 Dec 11. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. PMID: 35015425.(参照2025-2-15)
※5 Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. Dietary Reference Intakes for Japanese (2020 Edition). 2020.(参照2025-02-16)
※6 Spiegel K, Leproult R, Van Cauter E. “Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function.” The Lancet. 1999 Oct 23;354(9188):1435-9.(参照2025-02-16)
※7 Chang AM, Aeschbach D, Duffy JF, Czeisler CA. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Jan 27;112(4):1232-7. doi: 10.1073/pnas.1418490112. Epub 2014 Dec 22. PMID: 25535358; PMCID: PMC4313820.(参照2025-02-16)
※8 Horne JA, Reid AJ. Night-time sleep EEG changes following body heating in a warm bath. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1985 Feb;60(2):154-7. doi: 10.1016/0013-4694(85)90022-7. PMID: 2578367.(参照2025-02-16)
※9 Linde JA, Rothman AJ, Baldwin AS, Jeffery RW. The impact of self-efficacy on behavior change and weight change among overweight participants in a weight loss trial. Health Psychol. 2006 May;25(3):282-91. doi: 10.1037/0278-6133.25.3.282. PMID: 16719599.(参照2025-02-16)
著者プロフィール

佐藤 喜一
鍼灸師としての医学的観点とトレーナーとしての科学的視点をかけ合わせ「あなた本来の身体」へ導くパーソナルトレーナー
指導実績
トップアスリート、アーティスト、モデル、俳優などのトレーニング&コンディショニングを担当 これまでの経験を基に、トレーニングと鍼灸で1,000名以上の身体の悩みを抱える方々のサポートを行う
保有資格
◆はり師・きゅう師 ◆NSCA-CPT(認定パーソナルトレーナー) ◆FMS Level1 ◆テクニカ・ガビラン認定者